
不動産売買契約書は非常に大切な契約書類となりますが、聞きなれない言葉や言い回し、難解な専門用語も多用されていることから、内容が理解できていない人も多いと思います。
不動産売買の契約行為は、一生のうち何度もあることではないので、普段の日常生活で契約書の内容を目にする機会もほとんどないでしょう。そのため、売買契約条文の理解が不十分のまま契約を結んでしまう人もいると思います。
この記事では、不動産売買契約書の内容の理解が進むように、一般的な不動産売買契約で必ず盛り込まれる条文を抽出し、それぞれのポイントを解説しています。
不動産売買契約のポイントを理解しておけば、実際の契約締結の際にも、予備知識として役立つと思います。不動産の売買契約は初めてという方や、契約書のポイントだけでも理解しておきたいという方は、ぜひ参考にして下さい。
目次
不動産売買契約書の目的

不動産売買契約書は、不動産の売買を行う際に作成する書類で、売主と買主の権利や義務が記載されています。不動産の取引では、売主は買主に所有権を移転する義務を負い、買主は売買代金を支払う義務を負います。契約書にこれらの権利や義務を明確に記載することで、双方が安心して取引を進めることができます。
不動産は高額なので、売主と買主の間で解釈に相違があった場合、契約後に大きなトラブルに発展する可能性があります。こうしたトラブルを予防するために、物件の情報や取引の内容を書面にまとめたものが不動産売買契約書になります。
不動産売買契約書を作成することで、契約内容が明確になり、双方の合意事項を記録として残すことにより、トラブルが発生した場合でも、契約書の内容に基づいて解決を図ることができます。
不動産売買契約書は、不動産売買において重要な文書です。売買取引を円滑に進めるためにも、売主と買主は、契約書の内容をよく理解し、署名捺印をするようにしましょう。
不動産売買契約書の主な記載内容
一般的な不動産売買契約書に記される、主な内容について解説します。
売買目的物の表示
売買契約書では、表題部に「売買目的物」が表示されています。
具体的には、売買の目的となる不動産の地番、地目、地積、実測面積等が記載され、建物がある場合は、所在地・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。契約締結の際は、所在や数量等に間違いがないかを確認しましょう。
なお、不動産の引渡しまでに、現地において隣地との境界を明示し、売主・買主間で目的となる不動産の範囲等を確認しておく必要があります。
所有権の移転・引渡し・登記の日
売買契約書に記載される項目に「所有権の移転・引渡し・登記の日」があります。
一般的に、所有権の移転・引渡し・登記は、同時に行われます。売主が買主に不動産の所有権を移転するためには、売主が買主に不動産を明け渡し、買主が売主に売買代金を支払う必要があります。一方、買主が売主から不動産の所有権を取得するためには、登記を行う必要があります。
これらの手続きを同時に行うことで、売主と買主の権利義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐことができます。
手付金及び手付解除
手付金とは、契約が成立した証として、売買契約時に買主が売主に対して払う金銭です。
手付金は、引渡しまでの間に契約解除する際の違約金としての役割も果たします。
買主が契約解除をするときは手付金を放棄し、売主が契約解除をするときは手付金の倍額を返還します。売主だけ手付金の2倍の額が必要となりますが、売主はすでに買主から手付金を受領している状況であるため、売主も実質的な負担額は手付金の1倍です。
売買契約書には手付解除ができる期間も定められており、手付解除期間もチェックするポイントとなります。
負担の消除
「負担の消除」とは、不動産に抵当権等の権利が設定されている場合、これらの権利を売主の責任と費用負担にて抹消することを定めた規定になります。
抵当権とは、銀行等の債権者が担保物件から優先的に弁済を受けることのできる権利のことです。契約書上は引渡し時までに抵当権等を抹消することとなっていますが、住宅ローンが残っている物件を売る場合、実際には抵当権の抹消は、不動産の引渡しと同時に手続きを行います。抵当権抹消の登録免許税や司法書士手数料は売主の負担となり、抵当権抹消の根拠は、売買契約書の「負担の消除」で規定されることになります。
公租公課の精算
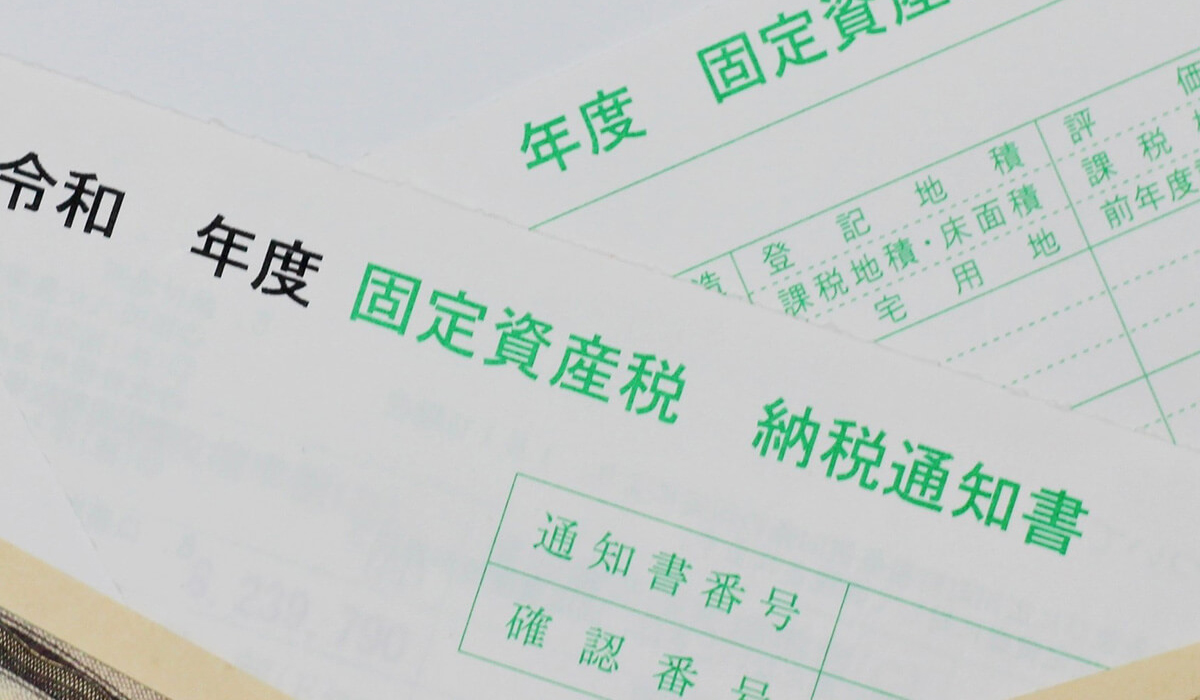
公租公課とは、固定資産税や都市計画税といった税金のことです。
不動産の売却では、商習慣として固定資産税等の精算を行います。固定資産税等の精算とは、引渡し日以降の固定資産税等の負担を買主へ移転するために買主が売主に対して支払う調整金のことです。
固定資産税等の精算は、本来は任意の行為ですが、当然のように行っているのは売買契約書に記載されていることが理由となります。具体的には、引渡し日以降のその年の固定資産税等を日割り計算したものが、買主が売主に対して支払う精算額となります。
危険負担
危険負担とは、現代風に表現すると「リスクテイク」のことです。不動産の売買は、売買契約から引渡しまで1ヵ月ほどの期間が空きます。
仮に引渡しまでの間に大地震が生じて不動産が滅失してしまった場合、そのリスクを誰が負うか(テイクするか)ということを定めているのが危険負担です。
不動産の売買契約書では、通常、危険負担は売主が負うものとしています。
つまり、引渡しまでに建物が滅失してしまったら、そのリスクは売主が取り、買主は売買代金を支払わなくても良いということです。売主が預かっていた手付金も、当然に買主へ返還することになります。
融資利用の特約(ローン特約)

融資利用の特約とは、買主が住宅ローンの本審査に通らなかったときの扱いを規定したもので、通称、「ローン特約」とも呼ばれています。
住宅ローンの本審査では銀行に売買契約書を提出する必要があることから、買主は住宅ローンの本審査に通っていない状態で契約を結ぶことになります。よって、売買契約後に買主が本審査を通らず、物件を購入できないということは理論的にあり得ます。
そのため、買主が住宅ローンの本審査に通らなかった場合は、融資利用の特約により売買契約は解除されます。売主は、融資利用の特約に従って手付金を返還することになります。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、契約の目的とは異なるものを売ったときに売主が問われる責任のことを言います。
2020年の民法改正により創設された新しい売主責任であり、以前に存在した瑕疵(かし)担保責任と類似するものです。
契約不適合責任では、売却後、買主が契約内容とは異なる部分を発見した場合、売主に通知することで責任を負ってもらいます。ただし、買主は購入後、永久に契約不適合責任を売主に問えるわけではなく、売買契約書に通知可能な期間を定めることが一般的です。
契約不適合責任の通知期間は、3ヵ月あるいは6ヵ月といった期間となります。通知期間は売主が契約不適合責任を負う可能性のある期間であり、短ければ売主に有利で、長ければ買主に有利です。
契約不適合責任では、通知期間が何ヵ月で設定されているかを確認することがポイントとなります。
締結すべき特約内容
契約不適合責任は売主にとって重たい責任であるため、特約を設けて契約不適合責任を免責することが一般的です。
契約不適合責任は、簡単に言うと契約内容とは異なるものを売ったときに売主に問われる責任になります。そのため、不具合があったとしても、その不具合を売買契約書の特約に明記しておけば、契約内容と異なるものを売ったことにはならず、契約不適合責任を問われることはありません。
契約不適合責任を免責するための文言としては、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 契約不適合責任を免責するための文例
- 本物件は築後長期間が経過しており劣化が著しく、屋根や壁、土台、基礎などに損傷が存在しており、雨漏り、沈下、傾斜などの不具合が生じていますが、買主はこれらを容認のうえで本物件を買い受けるものとし、売主に対して契約不適合責任を問わないものとします。
売主として免責したい内容は、建物の不具合だけでなく、土地の土壌汚染や地中障害物等もあります。
特約内容は、不動産会社が記載してくれることが一般的です。契約不適合責任の免責については不動産会社とよく相談し、事前に特約内容の文言を確認したうえで買主と契約を締結することが望ましいと言えます。
不動産売買を伴う土地活用のご相談は、ホームメイトの東建コーポレーションまで

以上、不動産売買契約書について解説しました。
土地活用においては、遊休地を売却し買い替えた土地に賃貸建物を建てるケースや、所有地の一部を売却してそこで得た資金を頭金にして賃貸建物を建てるケースなど、土地売買を伴う土地活用事例は増えています。
東建コーポレーションでは、経験豊富な不動産売買の専門スタッフが対応。土地売買を含む土地活用のご提案を承っております。
土地の購入や売却を伴う土地活用をご検討されている方は、ぜひ東建コーポレーションまで、ご相談下さい。






















 PAGE TOP
PAGE TOP



 電話でお問い合わせ
電話でお問い合わせ