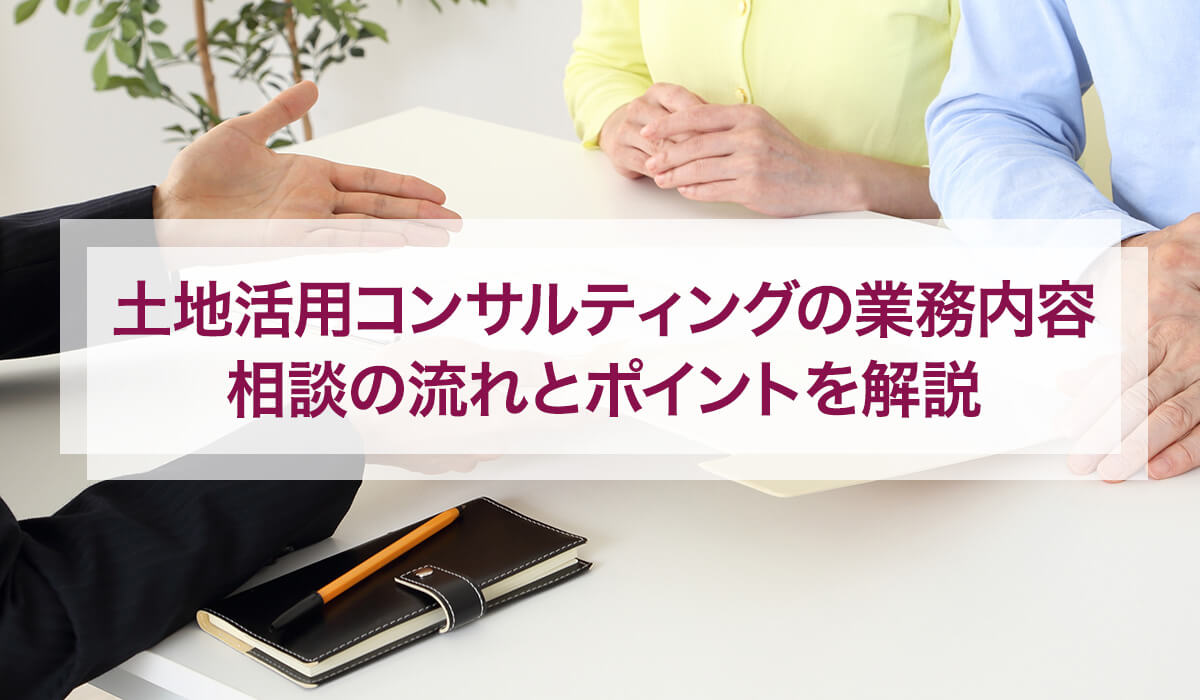
土地活用を適切に行うためには、土地活用の採算性や適切さを判断するための知識だけでなく、建築法規や税務、地域の賃貸需要、資金調達など、幅広い知識が求められます。
そのため、土地活用は複数の専門家から協力を得て計画を進めるのが通常と言えます。
そして、そんな専門家の中でも、土地活用の相談から必要情報の調査、具体的な事業計画の企画提案、プランニングに至るまで、一気通貫したサポートを行うのが、「土地活用コンサルティング」です。
この記事では、土地活用コンサルティングの業務内容について、詳しく解説していきます。
目次
土地活用のコンサルティング業務とは?
土地活用コンサルティングとは、土地活用に関する伴走型の支援を行うことを言います。伴走型の支援とは、文字通り相談者と並走しながら支援を継続することです。
土地活用コンサルティングでは、土地所有者様からご相談を受けてから、賃貸需要の調査や事業計画のプランニングを行い、土地所有者様の困りごとやお悩み解決の方法を具現化するまで、土地活用のトータルサポートを行います。
そのため、土地活用のコンサルティングを行うためには、専門知識だけでなく、その地域での実務経験に基づくノウハウが求められます。
なぜなら、土地は通常の商品やサービスとは比べものにならないくらい複雑な要素を持っている反面、様々な問題を解決できる可能性も持っているためです。
土地活用の計画として通常考えられるのは、金銭的な利益を得ることです。また、土地活用による相続税対策も、資産家の相続においては半ば常識というくらいに浸透しています。
しかし、実際の土地活用相談の内容は幅広く、かつ個別具体的であることが多いです。
例えば、借地権等の権利や法規制により活用が難しい土地の問題解決、土地に対する家族間の意見調整、賃貸経営の法人化による所得税対策など、まさにケースバイケースです。

土地活用コンサルティング需要の拡大
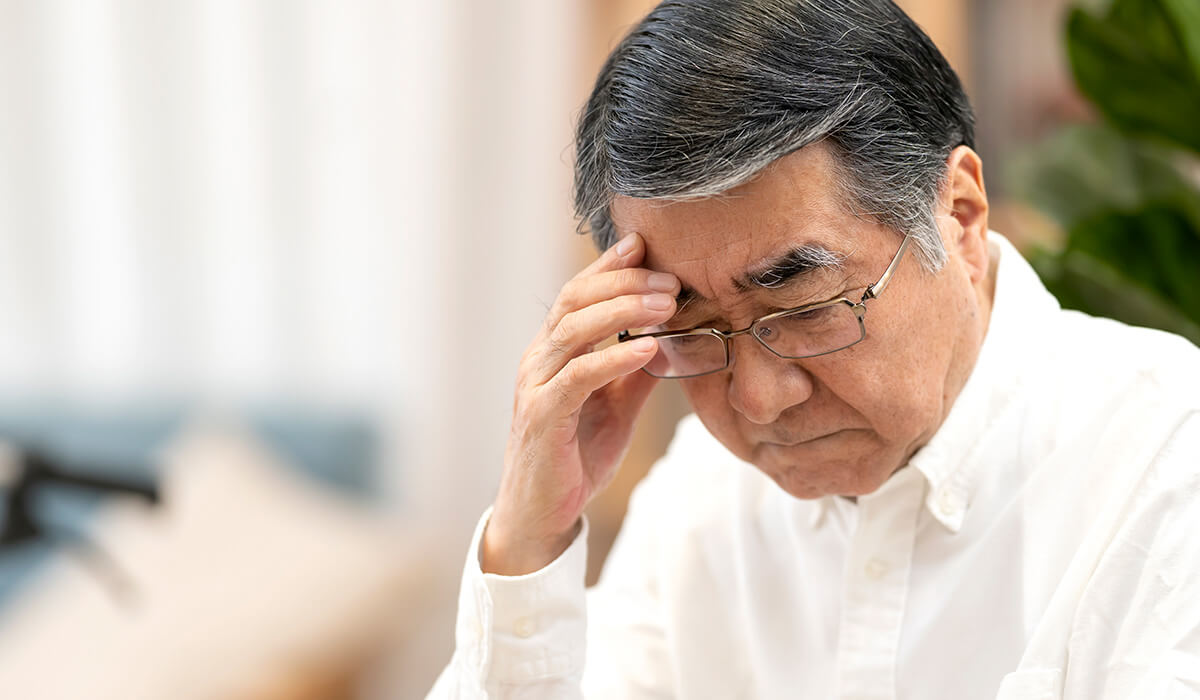
近年では、増税政策や社会保険料の増加、物価上昇などにより、土地所有者様の不動産に対する認識も変化してきました。
そのため、不動産を含めたすべての資産をバランス良く管理していこうという意識が高まり、所有する土地は有効に活用するべきという考えが強まっています。
これまでは、未利用地をそのまま放置することも良しとしていた土地所有者様が少なくありませんでしたが、現在では生活コストの増加等に伴い、相対的に土地を未利用地のまま保有する負担も大きくなっています。
さらに、今後も生活にかかる負担増が進んでいくと懸念されていることから、土地の有効活用を総合的にサポートする土地活用コンサルティングの需要が拡大しています。
土地活用コンサルティングの流れ
土地活用に関する様々なご相談への対応が求められる土地活用コンサルティングですが、業務の流れ自体は、共通している部分があります。土地活用コンサルティングの具体的な業務の流れは、下記のようになります。
【1】ご相談
最初に、土地所有者様からのご相談を受けます。
このときに、土地所有者様のお困りごとやお悩み、達成したいご希望条件等のヒアリングを行い、ご所有地の位置などを確認します。
また、ヒアリングの内容から、土地所有者様が気付いていないリスク等があればお伝えし、一緒に「土地活用を行う目的」を具体化していきます。
土地所有者様には、ご自身の問題を十分に認識した上で対策を考えている方もいますが、一方では、自分の置かれている状況や問題の深刻さを認識していらっしゃらない方も少なからず存在します。
そのため、土地活用コンサルティング業務は単なる御用聞きではなく、自ら問題点を指摘し、適切な選択肢を提示することも必要になります。
例えば、固定資産税の負担を解消したいが、借り入れはしたくないため、固定資産税がまかなえる程度でお金のかからない土地活用がしたいという土地所有者様がいたとします。
しかし、土地の場所(地価)と広さを聞いて相続税のリスクが濃厚と分かったため、まずは想定される相続税額を税理士に計算してもらうという選択肢を、土地所有者様に提示するといった流れです。
このように、土地所有者様のお悩みを真摯に受け止めながら、適宜、必要情報の提供や選択肢の提示を行い、土地所有者様と一緒に土地活用の目的を考えることが、相談段階での土地活用コンサルティング業務となります。
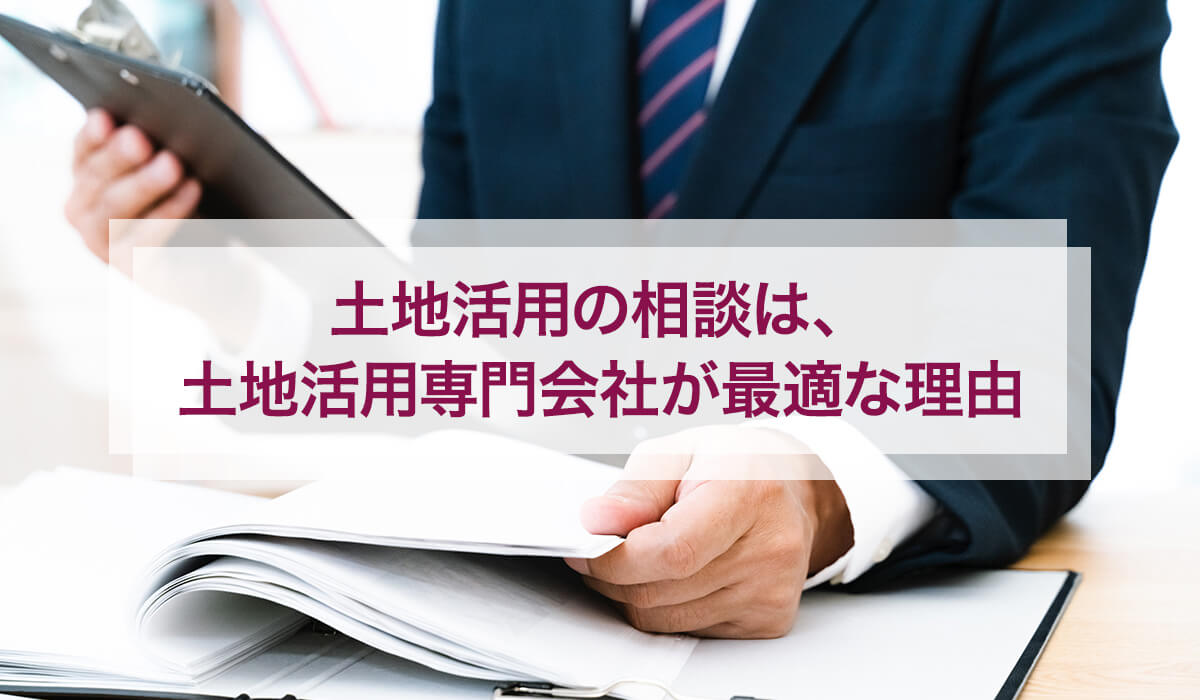
【2】市場調査・敷地調査
土地活用を行う目的が定まったら、土地の市場調査と敷地調査を実施します。
土地活用に失敗しないためには、賃貸需要が見込める土地活用方法を選択することが必須となるため、市場調査を実施して、土地に適した土地活用方法を絞り込みます。
一方、土地の広さや形、建築基準法や都市計画法などの建築法規により、実現できる土地活用方法と、できない方法があります。
また、ライフラインの敷設状況等によっては、土地活用の種類ごとに工事費の負担も変わってきます。
一方、土地の広さや形、建築基準法や都市計画法などの建築法規により、実現できる土地活用方法と、できない方法があります。
また、ライフラインの敷設状況等によっては、土地活用の種類ごとに工事費の負担も変わってきます。
そのため、敷地調査を実施して、土地の面積や高低差、接道状況、権利状況(所有権、共有、借地権・底地権等)、法的規制(都市計画法、建築基準法、条例・要綱等)、周辺状況(交通量、周辺施設、街並み、自然環境等)の調査を行います。
こうして、賃貸需要が見込めて、実現可能な土地活用方法を絞り込みます。
その上で、土地活用を行う目的を達成できる方法を選定することになります。
市場調査・敷地調査では、一級建築士や入居仲介のスタッフを始め、必要に応じて土地家屋調査士や司法書士等の外部協力者とも連携して作業を行います。
また、この段階で土地の登記簿謄本や公図、地積測量図などの必要資料を集め、具体的な事業計画を検討するための下準備を行います。


【3】プランニング
目的を達成するための具体的な土地活用方法が定まったら、土地活用のプランニングを実施します。
土地活用のプランニングは、収益の確保や相続税対策、スムーズな資産の承継等、相談者様のニーズによって、目指すべきゴールも異なってきます。その上で、収入に占める支出のバランスを適正な範囲におさめる収支計画や、金融機関からの融資を調達するための資金計画を検討します。
なお、プランニングの際に最も注意すべき要素として、適正な家賃設定をすることと、適切なリスク対策を講じておくことの2つが挙げられます。
家賃設定は、高すぎると空室リスクが増加し、低すぎれば収益性が損なわれるため、高すぎず低すぎない、ちょうど良い金額にする必要があります。
リスク対策としては、まず、事業計画の内容に空室や家賃減少などストレスをかけ、リスクの大きさを確認します。
リスクが許容できない程大きければ事業計画を見直し、リスクが低い、もしくは一定の対策を講じることで低く抑えることができるのであれば、事業計画を進めます。
具体的なリスク対策の方法としては、一定の自己資金を投入することや5年後や10年後の繰り上げ返済を計画しておく等が挙げられます。

【4】ご提案
プランニングした土地活用計画を、土地所有者様にご提案します。
ご提案は、土地活用の計画を落とし込んだ「配置図」と、収支計画や資金計画などをまとめた「事業計画書」をもとに行います。
併せて、ご相談からご提案に至るまでの経緯と要点をまとめた「おさらい」の資料があれば、ご提案内容の意味が分かりやすくなります。
なお、土地活用のご提案は、土地所有者様だけではなく、ご家族全員に対して行うことが適切と言えます。
土地活用を行う主な目的

土地活用を始める場合、まずは目的があり、それを具現化するための調査やプランニングを実施することで計画を進めていくことになります。
では、土地所有者様は、実際にどんな目的で土地活用を始めているのでしょうか。
ここでは、土地活用の目的について、比較的オーソドックスな例をご紹介します。
土地の収益化
土地活用の最もオーソドックスな目的としては、土地の収益化が挙げられます。
土地は、活用しなければ収益を生まず、むしろ負担が生じるという特徴を持つ資産です。
そのため、土地の価値を収益化するには、土地活用を行うことが前提条件となります。
土地の収益化は、「このままではもったいないから、土地を上手く使いたい」というニーズに基づいた土地活用の目的と言えます。
そのため、土地に焦点を当てて土地活用計画の企画を立てることがポイントになります。
具体的には、土地の立地条件や広さ・形などに応じて、賃貸需要が見込める、その土地にあった土地活用方法を選択するということになります。
これは他の目的で土地活用を行う場合にもベースとなる考え方です。

相続税対策
相続税対策も、オーソドックスな土地活用を行う目的と言えます。
相続税対策を目的に行う土地活用では、相続税の評価方法に着目し、相続税評価が高く見積もられる資産を、低く見積もられる資産に変えることが主眼となります。
具体的には、相続税評価が高い「現金」を、低い「建物」に変えることや、同様に相続税評価が高い「更地」を、低い「貸家建付地」に変えることなどです。
また、借入金を利用することでマイナスの財産を持つことができるため、プラスの財産と相殺(債務控除)することもできます。
ポイントは、引き下げているのはあくまで相続税の評価額であり、時価や実勢価格ではない点です。
そのため、本当の意味で資産が減少してしまうわけではありません。
適切な土地活用方法としては、賃貸マンションやアパートなどの賃貸住宅経営が挙げられます。
賃貸住宅経営による相続税対策の基本的な流れは、下記のようになります。
スクロールしてご覧下さい
| 賃貸住宅経営による 相続税対策の流れ |
大まかな計算式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ 銀行から融資を受けて「現金」を借り入れる |
|
|||||||
| ❷ 相続税評価の高い「現金」を、低い「建物」に変える |
|
|||||||
| ❸ 「建物」を「貸家」とすることで、さらに相続税評価が下がる |
|
|||||||
| ❹ プラスの財産からマイナスの財産を差し引く(債務控除) |
|
上表を見ると、1億円の借入金で賃貸住宅経営を始めた場合、債務控除後の財産はマイナス5,800万円となりました。
このマイナス5,800万円は、さらに自宅や預貯金といった他の財産と債務控除することが可能です。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですので、仮に法定相続人が配偶者と子2人の場合、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」で、4,800万円が基礎控除額となります。
この場合、相続財産が債務控除額の5,800万円と基礎控除の4,800万円を足した、1億600万円以内であれば、相続税をゼロにできることになります。
その上で、賃貸住宅経営を行うことで、下表の税制上のメリットを得ることができるため、
ご所有地の相続税評価を引き下げることもできます。
スクロールしてご覧下さい
| 賃貸住宅経営による 制度の名称 |
効 果 |
|---|---|
| 貸家建付地の評価減 | 賃貸住宅の敷地であれば、借地権と借家権の分、土地の相続税評価額が下がる。(概ね85%前後になる) |
| 小規模宅地等の特例 | 賃貸住宅の敷地であれば、200㎡まで土地の相続税評価額が50%になる。 |
賃貸住宅経営による相続税対策について、さらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

老後資金の確保
老後資金の確保を土地活用の目的とする方も多くいらっしゃいます。
財団法人生命保険文化センターによると、老後に必要となる生活資金は、夫婦で月額約28万円が平均とされており、ゆとりある老後を過ごしたい場合、夫婦で月額約36万円が必要とされています。
また、近年では、老後資金2,000万円問題も世間を騒がせました。
老後資金2,000万円問題とは、老後の生活資金として、公的年金以外に2,000万円が必要になるという試算です。2019年6月に公表された金融庁の報告書「高齢社会における資産形成・管理」に上記内容の記載があったことで、大きな話題となりました。
さらには、少子高齢化による高齢者福祉の持続性についての不安、物価上昇による相対的な年金の価値減少に関する懸念などから、老後資金の備えを意識する方は増えています。
老後資金の確保を目的として土地活用を行う場合、収益性と安定経営を主眼とした事業計画を企画するのが適切です。
例えば、後30年で2,000万円の資金を確保したい場合、30年は360ヵ月ですので、2,000万円を360ヵ月で割った約5.6万円を、毎月安定して稼いでくれる方法であれば、土地活用の目的を達成することができます。
注意点としては空室が生じたり家賃が減少したりするリスクや修繕費などの支出も踏まえて計画を検討する必要がある点が挙げられます。
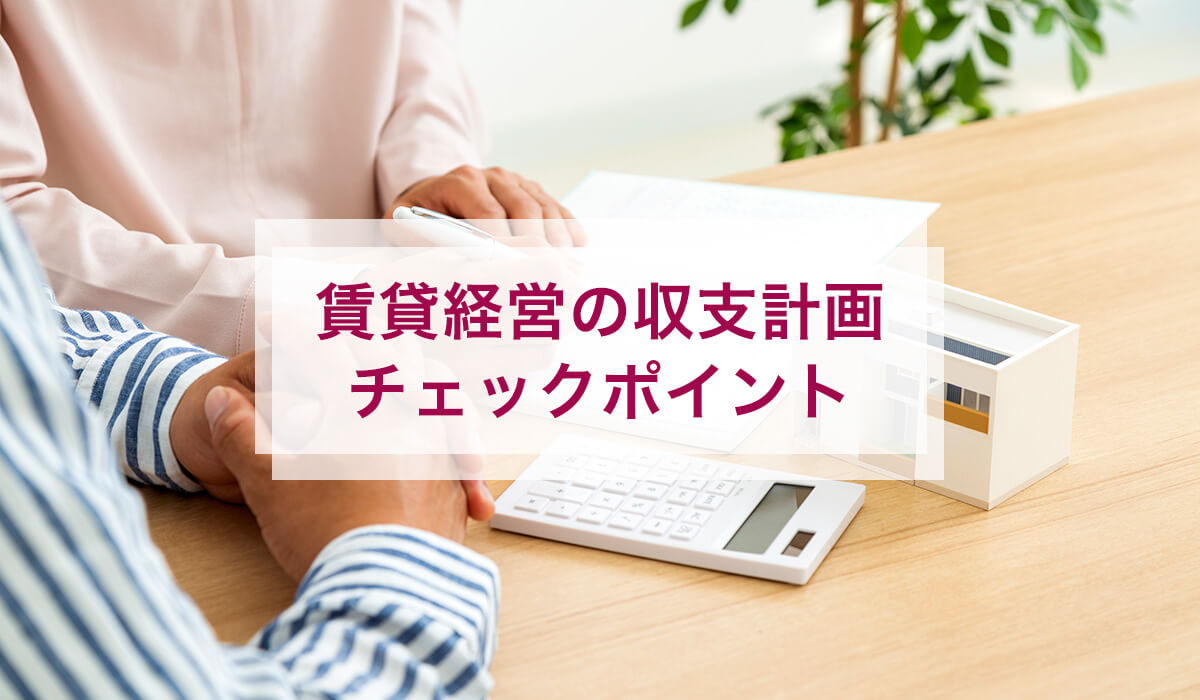
土地活用コンサルティングを受ける際に必要な資料
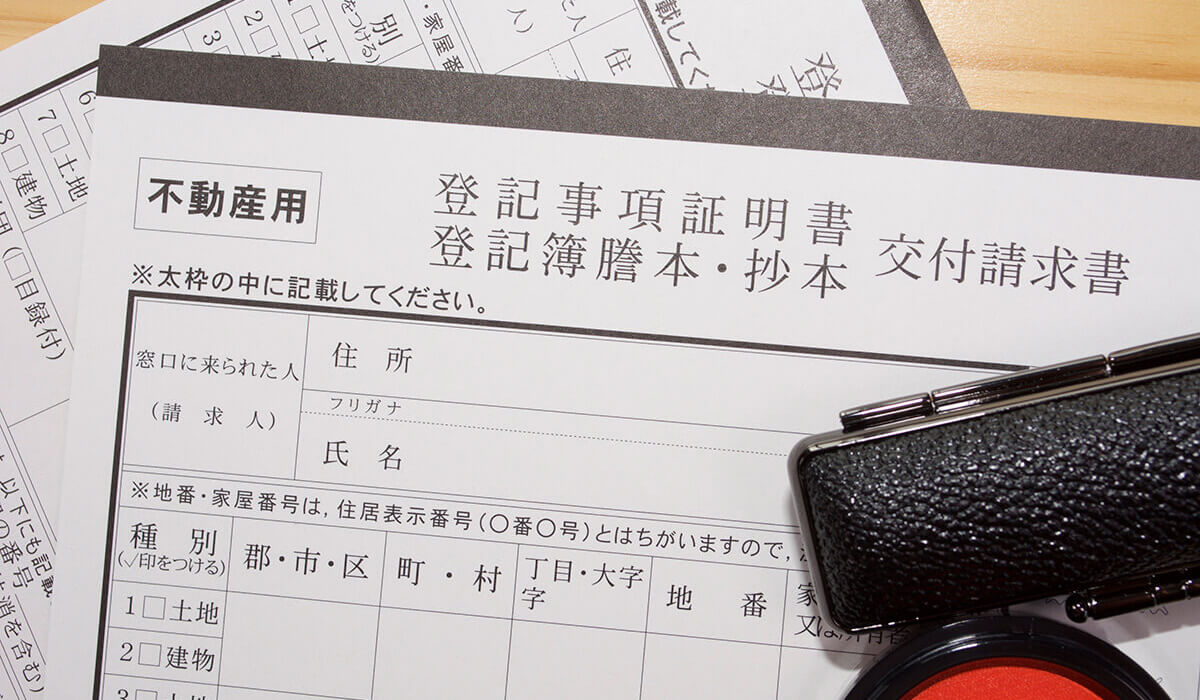
ここでは、土地活用コンサルティングを受ける際に必要な資料についてご紹介します。
結論を言えば、「漠然とした相談内容」と「ご所有地の場所」を口頭で伝えることができれば、土地活用の相談は成立します。
ご所有地や土地所有者様の現状を把握する段階から、土地活用コンサルタントと一緒に進めていけば良いためです。
しかし、事前に用意しておくことで相談がスムーズに進む資料はあります。具体的には、以下のような資料です。
スクロールしてご覧下さい
| 資料の名称 | 取得できる場所 | 資料で分かること |
|---|---|---|
| 登記簿謄本 | 法務局 | 所在や面積、権利関係などの土地情報 |
| 公 図 | 法務局 | 土地の大まかな形や隣地の地番、周辺の赤道・青道等の情報 |
| 地積測量図 | 法務局 | 土地の正確な形が分かり、土地が測量済みである証にもなる |
| 固定資産税台帳 | 市区役所 ・町役場 |
市区町村内に所有する不動産の情報 |
| 家系図 | 手書きで良い | 相続人の人数や将来的に想定されるライフイベント等 |
| 既存の土地活用資料(レントロールや返済予定表等) | 賃貸管理会社 金融機関 等 |
収支バランスや空室等の問題点、所得税負担の大きさなど |
土地活用の計画を具体化する段階や、融資相談をする段階では、他にも必要な資料がありますが、相談の段階では、ひとまず上表の資料があれば十分と言えます。
その他の情報については、口頭で伝えた上で、必要に応じて具体的な資料を確認すれば問題ありません。
土地活用に必要な「登記簿謄本」の基礎知識
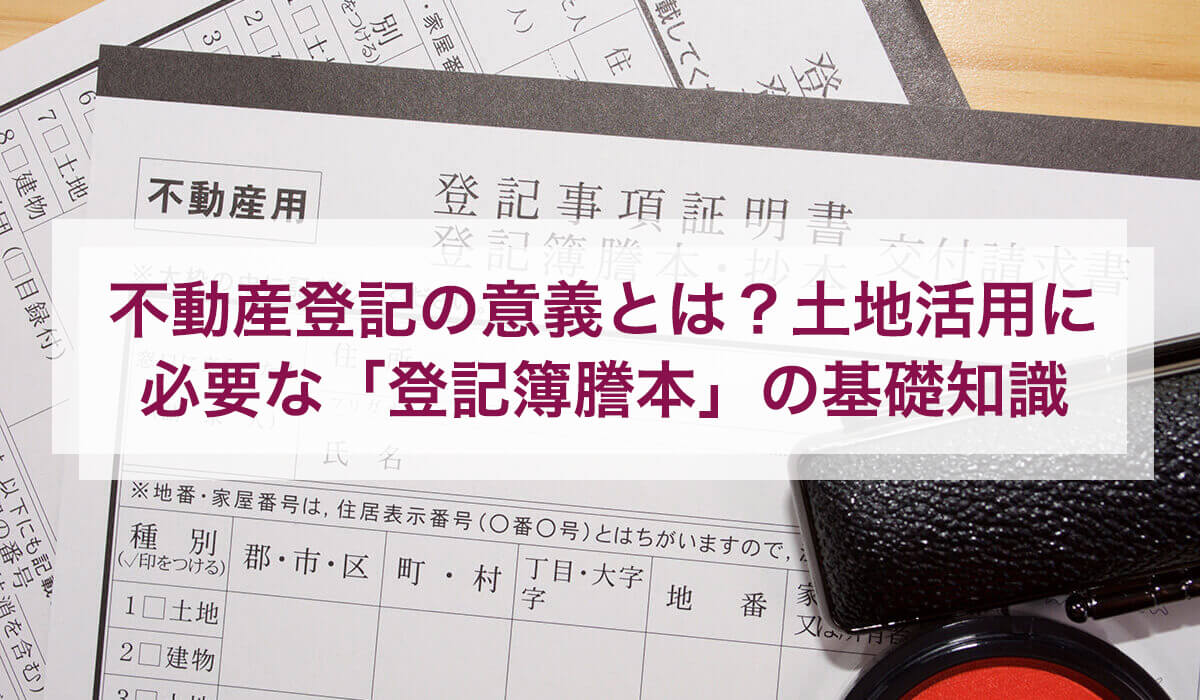
土地活用コンサルティングを有効に利用しよう
以上、土地活用コンサルティングの業務内容についてご紹介しました。
近年、増税等の負担増や物価上昇などに伴い、未利用地を有効に活用したいという方が増えており、これに伴い、土地活用コンサルティングの需要も増加しています。
土地活用コンサルティングとは、土地活用についてなんらかの方向性や方針を決めるより前の、現状を把握する段階から相談が始まります。
基本的には、始めから最後まで、土地所有者様と一緒に進めるのが土地活用コンサルティングです。
土地活用のコンサルティングでは、土地所有者様からお悩みや、困りごとのヒアリングをするだけでなく、土地所有者様が自覚していない問題点に気付いて提示することも業務内容としています。
土地活用コンサルタントは、土地活用のアドバイザーであり、ガイドであり、調査員であり、プランナーです。
土地活用について知りたいことや案内して欲しいこと、調べて欲しいこと、そして具体的なプランを考えて欲しいといった様々なご要望に対応することができます。
土地活用をご検討の方は、ぜひ、土地活用コンサルティングの実績豊富な東建コーポレーションまで、お気軽にご相談ください。

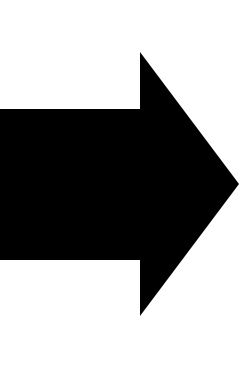





















 PAGE TOP
PAGE TOP



 電話でお問い合わせ
電話でお問い合わせ