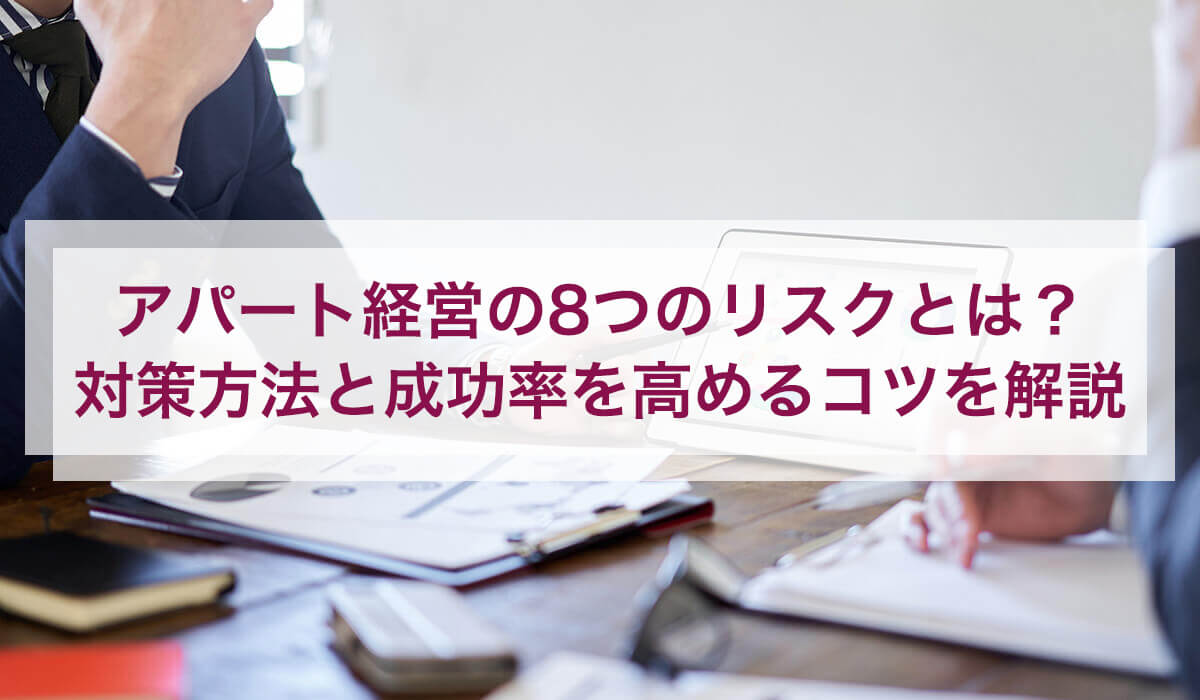
アパート経営は、長期に安定した収益が得られる土地活用方法として知られていますが、投資である以上、一定のリスクが存在することを忘れてはいけません。
この記事では、アパート経営の8つのリスクをメインに、具体的な対策方法と成功率を高めるコツについてご紹介します。アパート経営で失敗しないためにも、ぜひご参考になさってください。
スクロールしてご覧下さい
| アパート経営のリスク | 対策方法 |
|---|---|
| 【1】空室リスク | 賃貸需要が見込める立地でアパート経営を行う |
| 【2】競合物件が発生するリスク | 他の物件との差別化を図る |
| 【3】賃料が下落するリスク | 空室を増やさない 空室期間を長引かせない |
| 【4】借入金返済リスク | 空室リスクを拡大させない 自己資金の割合を増やす |
| 【5】修繕リスク | 修繕費を計画的に積み立てる |
| 【6】家賃滞納リスク | 家賃保証会社を立てる |
| 【7】入居者トラブルが発生するリスク | 管理会社に入居審査をしっかりと行ってもらう |
| 【8】金利上昇リスク | 固定金利を利用する 自己資金の割合を増やす 繰り上げ返済を利用する |
目次
アパート経営の8つのリスクと対策方法

アパート経営は、他の土地活用方法に比べて比較的安定した収益を得られますが、投資である以上、失敗する可能性はゼロではありません。
そのため、アパート経営を始める際は、どのようなリスクがあるのかを理解しておくことが重要です。ここでは、アパート経営における8つのリスクとその対策方法をご紹介します。
- 【1】空室リスク
- 【2】競合物件が発生するリスク
- 【3】賃料が下落するリスク
- 【4】借入金返済リスク
- 【5】修繕リスク
- 【6】家賃滞納リスク
- 【7】入居者トラブルが発生するリスク
- 【8】金利上昇リスク
【1】空室リスク
アパート経営において最大のリスクと言われるのが空室リスクです。空室リスクがアパート経営で最大のリスクと呼ばれる理由は、賃料下落リスクや借入金返済リスクなど、あらゆるリスクの呼び水となるためです。
空室リスクは様々な原因によって生じますが、最も大きな原因に「立地」があります。
アパート経営は典型的な立地産業であるため、賃貸需要の低いエリアで無理にアパート経営を行っても十分な収益を得られず、事業として成り立ちません。
空室リスクを防ぐには、賃貸需要が相応に存在する立地でアパート経営を行うことが重要です。
【2】競合物件が発生するリスク
アパートは、賃貸マンションに比べて投資額が低く、比較的小さな土地にも建築できることから、競合物件が増えやすい傾向があります。
一般的に賃貸住宅は、築年数が経過していない新築物件の方が、入居者様が集まりやすくなるため、周辺に新しいアパートが建つと、ご所有のアパートの競争力が弱くなってしまいます。
競合物件リスクを回避するためには、物件の差別化が重要になります。例えば、ペット相談可にしたり、専用庭や広いバルコニーが付いたガーデニング設備を導入したりすることで、他の賃貸住宅との差別化を図ることができます。

【3】賃料が下落するリスク

アパートの賃料が下落するリスクは、前述した「空室リスク」がきっかけとなって生じます。
築年数の経過や競合物件の発生などを原因に空室が増えていくと、今までと同じ募集賃料では入居者様が集まりにくくなるため、賃料を下げざるを得ない状況になってきます。
また、長い間空室があるアパートの場合、そのアパートがいくらの賃料で入居募集を出しているのか、居住中の入居者様が調べるケースが出てきます。
その結果、自分が払っている賃料よりも低い賃料で募集がかけられていることが分かると、自分の賃料も下げてほしいと要求してくることも少なくありません。
このような賃料下落リスクを防ぐには、空室を増やさない、もしくは空室期間を長引かせないことが最大の対策となります。
【4】借入金返済リスク
借入金返済リスクとは、アパート経営で得られる毎月の家賃収入が減ることによって、当初予定した通りには借入金が返済できなくなるリスクのことです。
借入金返済リスクも空室リスクが呼び水となって生じ、具体的には、空室を埋めるために募集賃料を下げた結果、家賃収入から借入金を返済することが難しくなってしまったなどのケースが該当します。
借入金返済リスクは、「空室リスクを拡大させない」、「自己資金の割合を増やす」という2つの対策によって発生を抑えることができます。ひとつ目の「空室リスクを拡大させない」という対策には、立地の良い場所でアパート経営を行ったり、他の物件との差別化になる設備や建物仕様を導入したりする方法があります。
2つ目の「自己資金の割合を増やす」という対策は、アパートローンを借りる際に自己資金の割合を増やして、返済すべき借入金の金額を減らすことを指します。
借入金が少なければ毎月の返済額が減るため、多少の空室が発生してもキャッシュフローの悪化を抑えることができます。借入金返済リスクはアパートの経営状況だけが原因になるのではなく、オーナー様の資金力も影響してくることを理解する必要があります。
【5】修繕リスク
アパート経営における修繕リスクとは、建物の経年劣化や通常損耗に伴って、多額の修繕費が発生することです。
アパートの経年劣化や通常損耗については、オーナー様が修繕費を負担するものと定められています。
経年劣化とは、時間の経過と共に建物の品質が低下することで、日照によるクロスの日焼けやフローリングの変色などが該当します。
通常損耗とは、日常生活を送る上で生じた傷や汚れのことで、具体的には、家具を配置したことで生じる床のへこみや、壁の電気焼けなどを指します。
経年劣化や通常損耗は、アパートの築年数が経過するほど増え、それに比例してオーナー様が負担する修繕費も増えていきます。
加えて、設備の交換や外壁塗装工事についても、同様に負担する必要があります。
修繕費リスクについては、修繕費を計画的に積み立てておくことが対策となります。
大規模修繕に備えるには長期修繕計画を立てることが有効であり、長期修繕計画は、土地活用専門会社などが作成してくれることが多いため、アパート経営を始めたら、土地活用専門会社等に相談することをおすすめします。
【6】家賃滞納リスク
アパート経営では入居者様が家賃を滞納するリスクも考えられます。以前は家賃滞納の対策として、敷金を高く設定したり、連帯保証人を必須条件にしたりすることで保険をかけることができましたが、これらは入居を決める上で避けられやすい要素でもあるため、入居者様が集まりにくくなります。
また、敷金を設定できたとしても1ヵ月程度しか取れない場合も多く、家賃滞納の担保としては心もとない金額と言えます。
そのため、近年では「家賃保証会社」を立てて、家賃滞納リスクを保全することが一般的となっています。家賃保証会社とは、家賃収入をオーナー様に保証する会社のことです。入居者様が家賃を支払わなかった場合に、保証会社が代わりに支払ってくれるため、滞納が生じてもオーナー様は損失を負担せずに済みます。
【7】入居者トラブルが発生するリスク
アパートは、ひとつの建物に複数の入居者様が暮らす集合住宅であるため、入居者様同士のトラブルが発生するリスクもあると理解しておく必要があります。
具体的なトラブル例としては、「騒音」や「悪臭」、「ペット禁止物件での飼育」、「契約者以外との同居」などが挙げられます。
賃貸住宅で発生するトラブルの中には、他の入居者様に影響を及ぼすものもあり、最悪の場合、トラブルに耐え兼ねた入居者様が退去してしまうというケースもあります。
入居者様同士のトラブルを回避するためには、管理会社に入居審査をしっかりと行ってもらうことが重要です。
管理会社を選ぶ際は、アパートの管理実績が豊富な会社を選ぶようにしましょう。

【8】金利上昇リスク
これからアパート経営を始める方や、アパートローンを変動金利で組んでいる方は、将来的に金利が上昇するリスクが発生する可能性があることも理解しておく必要があります。
金利が上昇すると借入金利子返済額が増えるため、借入金元本の返済が予定通りに進まなくなる恐れがあります。
また、金利が上昇すれば、アパートをはじめとする賃貸住宅は買いづらく、建てづらくなるため、価格が下落します。
そのため、売却しようとしてもアパートの価格が下がってしまい、売却益だけでは借入金(残債)を返済できない可能性も出てきます。
金利上昇リスクに備えるためには、「固定金利を利用する」、「自己資金の割合を増やして借入金の額を減らす」、「繰り上げ返済を利用する」などの方法が効果的です。

リスクを抑えてアパート経営の成功率を高めるコツ

ここからは、リスクを抑えてアパート経営の成功率を高める4つのコツをご紹介します。
❶リスクを考慮した収支計画を立てる
アパート経営は長期にわたる事業のため、初期費用だけでなく、税金や諸経費などの継続的な費用もかかります。
そのため、様々なリスクや、それに伴う支出を考慮した上で、ご自分にとって無理のない収支計画を立てることが重要です。
長期的な収支計画を立てずにアパート経営を始めた場合、設備の交換や外壁塗装などの大規模修繕、入居者様の家賃滞納、災害時の建物トラブルなどが想定外の支出となり、最悪の場合、事業が成り立たなくなる可能性があります。
アパート経営を始める際は、万が一の事態にも対応できるよう、リスクを考慮した収支計画を立てましょう。
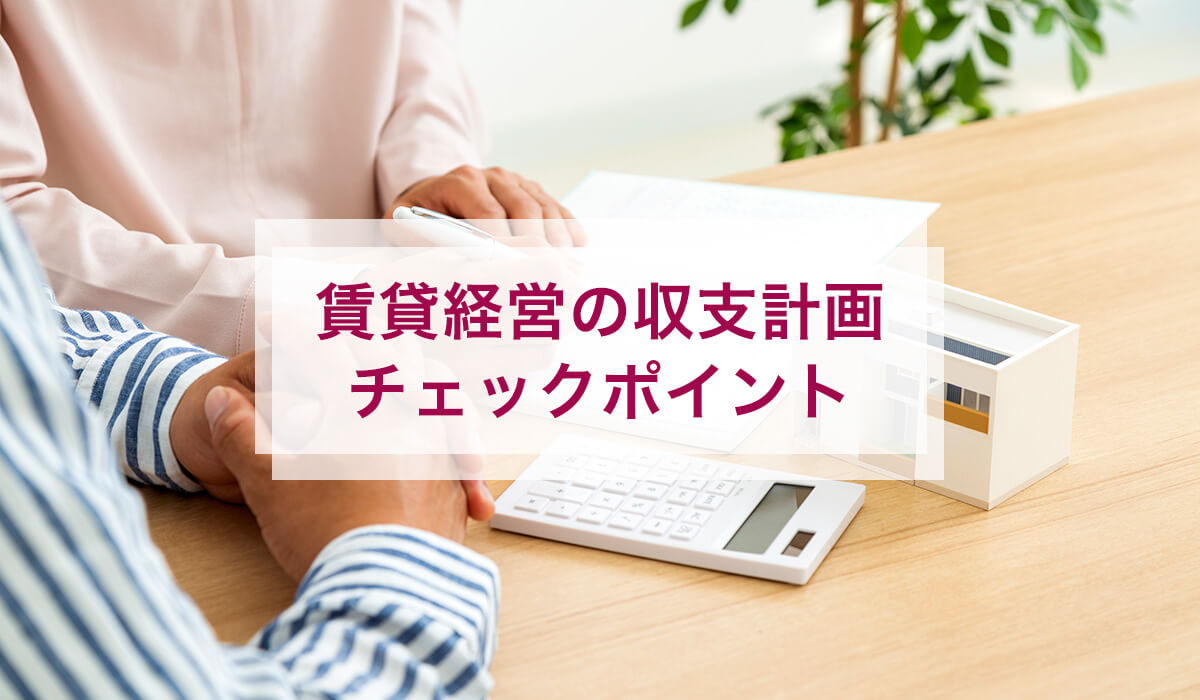
❷市場調査を実施する
アパート経営をはじめとする土地活用において、市場調査の実施は、最も重視されるポイントです。
アパート経営が成功するかどうかは、市場調査データに基づいて作成された事業計画の精度で決まると言っても過言ではありません。
土地活用の市場調査では、オーナー様が所有する土地で、どれくらいの賃貸需要が見込めるのか、どのような規模のアパートが建てられるのか、どういった間取りタイプが適しているのかなどを総合的に調査します。
市場調査データに基づいて、事業計画を立てることで、空室リスクを最小限に抑えることができ、長期に安定した収益を得られる可能性が高まるでしょう。

❸アパート経営に関する知識を蓄えておく
アパート経営には、不動産はもちろん、税金や法律、会計などの様々な知識が必要です。
土地活用専門会社や管理会社などに相談したり、アパート経営自体を委託したりすることもできますが、オーナー様自身が最低限の知識を蓄えておけば、経営における様々な選択を自らの判断で行えるようになります。
また、アパート経営においては、人気の設備や仕様、暮らしのトレンドに関する知識なども身につけておくことが望ましいです。
求められる設備に対応した賃貸物件を建築することで、様々なリスクに対応しやすくなるでしょう。

❹豊富な知識とノウハウを持つ土地活用専門会社に相談する
前述したように、アパート経営のリスクは多岐にわたるため、すべてを完全に回避することは困難です。
しかし、どのようなリスクがあるのかを把握し、あらかじめ対策を講じることで、リスクを最小限に抑えることはできます。
そのためには、アパート経営に精通した会社をパートナーとして選び、ノウハウを利用することが欠かせません。
アパート経営のパートナーには、「土地活用専門会社」を選ぶのがおすすめです。
土地活用事業の業務範囲は幅広く、本来ならば建築会社と設計会社、不動産会社の3つの会社に相談する必要があります。
しかし、土地活用専門会社は建築会社でありながらも、社内に一級建築士が在籍する設計会社としての機能を持ち、さらには仲介と管理を行う不動産会社としての機能も持っています。
事業の工程に応じてつど、別の会社に相談したり、情報を共有したりする必要がないため、手間と時間を抑えながらスムーズにアパート経営の相談ができます。
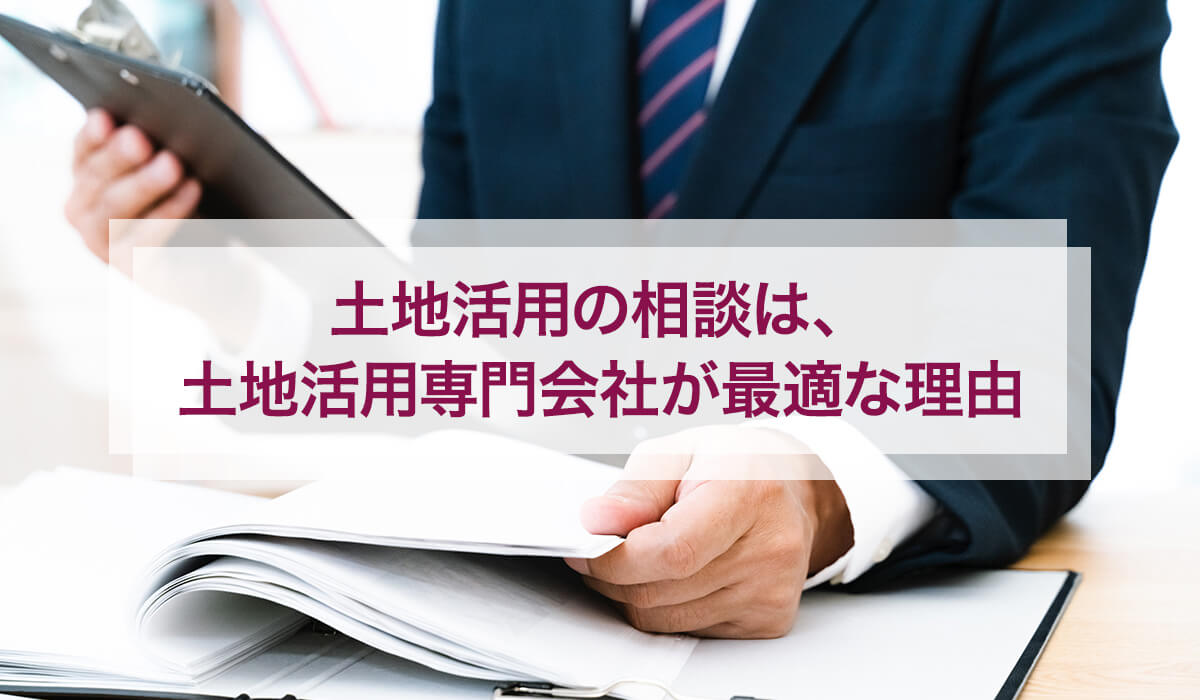
リスクを抑えたアパート経営を実現したいオーナー様は東建コーポレーションまでご相談ください
以上、アパート経営の8つのリスクとその対策方法について解説しました。
アパート経営のリスクには、「空室リスク」や「競合物件が発生するリスク」、「賃料が下落するリスク」などがあり、賃貸需要が相応に存在する立地でアパート経営を行ったり、他の物件との差別化を図ったりすることで対策を講じることができます。
なお、リスクを抑えてアパート経営の成功率を高めるには、「リスクを考慮した収支計画を立てる」や「市場調査を実施する」、「豊富な知識とノウハウを持つ土地活用専門会社に相談する」などの方法が効果的です。
東建コーポレーションは土地活用専門会社であるため、アパート経営の始まりから終わりまで、ワンストップでご対応いたします。
長年培ったノウハウと知識を活かして市場調査を実施したり、長期に安定した収益を得られるような事業計画のプランニング作成をしたりすることも可能ですので、アパート経営による土地活用をお考えのオーナー様は、ぜひ東建コーポレーションまでお気軽にご相談ください。






















 PAGE TOP
PAGE TOP



 電話でお問い合わせ
電話でお問い合わせ