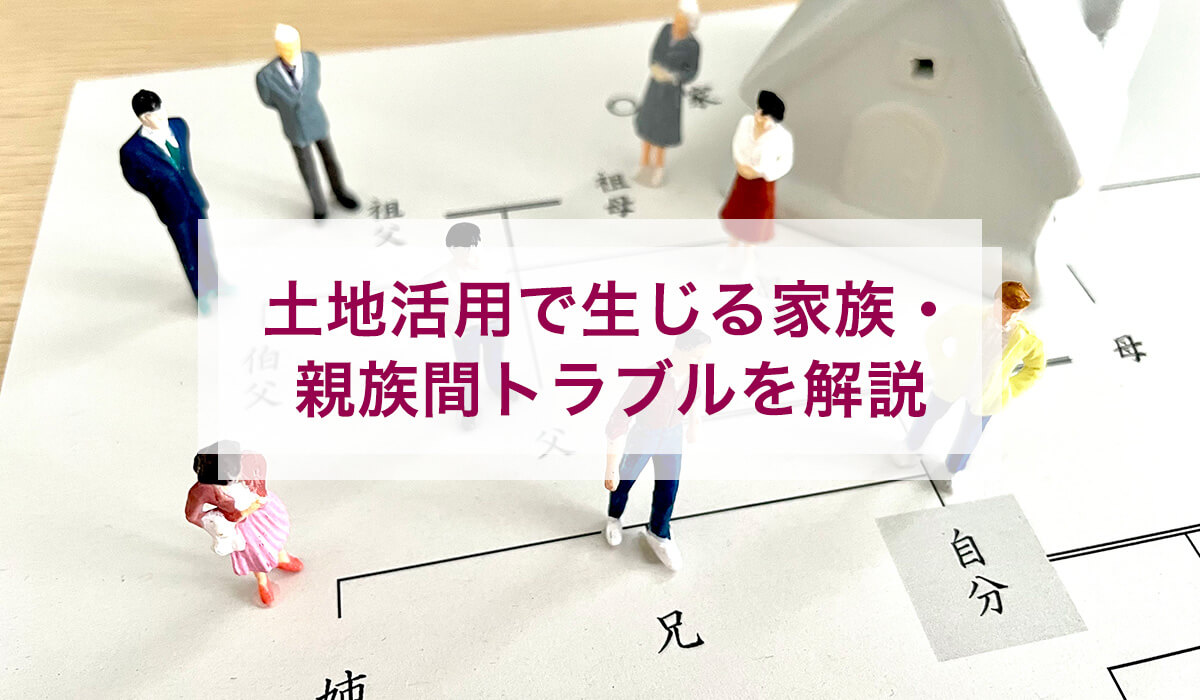
家族にとって良かれと思って行う土地活用でも、のちに家族・親族間でトラブルの火種となってしまうことがあります。
家族・親族間のトラブルを発生させないようにするには、なぜ土地活用がトラブルの原因になり得るのかを知っておくことが望ましいと言えます。
特に相続税対策で土地活用を行う場合、相続後に発生する可能性のある問題を事前に把握し、対策をしておくことが適切です。この記事では「土地活用で生じる家族・親族間トラブル」について解説します。
目次
土地活用と相続税の節税効果
最初に、土地活用がなぜ相続税を節税できるかについて解説します。
土地活用は、相続税対策のために行う人が多いです。
相続税は、土地や建物、株式・公社債等の有価証券、預貯金、現金の資産や債務(マイナスの財産)等を対象にした遺産の総額に対して課税額が計算されます。
このうち、時価の把握が難しい土地や建物に関しては、財産額を一定のルールに基づき計算して良いことになっています。
具体的には、土地は相続税路線価に基づいて求められた価額、建物は固定資産税評価額に基づいて求められた価額です。
一例として、マイホームのような自分で使っている不動産の評価額は以下のようになります。
スクロールしてご覧下さい
| 土地 | = | 自用地としての価額 (相続税路線価に基づいた額) |
| 建物 | = | 建物の固定資産税評価額 |
土地活用を行い、不動産が自用地から賃貸物件になると相続税評価額を以下のように計算することができます。
スクロールしてご覧下さい
| 土地 | = | 自用地と しての価額 |
× | ( 1 | - | 借地権割合 | × | 借家権割合 | × | 賃貸割合 ) |
※借地権割合を50%、賃貸割合100%とした場合

スクロールしてご覧下さい
| 建物 | = | 建物の固定資産税評価額 | × | ( 1 | - | 借家権割合 | × | 賃貸割合 ) |

借地権割合は30∼90%の範囲で定められた数値、借家権割合は全国一律で30%となります。
賃貸割合とは相続時における入居率のことです。
賃貸物件は、上記のような評価減が適用されるため、最終的に相続税評価額が時価の3∼4割程度となることもあります。
実際の資産価値よりも大幅に下がった金額を財産額とすることができることから、相続税を節税することができるのです。
土地活用による相続対策の課題
土地活用は確かに相続税の節税をする効果はありますが、同時に相続人の間で遺産を分割しにくくなるという問題を生んでしまいます。
相続人が2人の子だけの場合、子は本来であれば50%ずつ遺産を譲り受ける権利があります。
しかしながら、例えば、賃貸マンションが1.8億円、現金が2,000万円というように、遺産の割合が極端に不動産に偏っているケースも少なくありません。
この場合、1人が賃貸マンション、もう1人が現金を引き継ぐと、9対1の割合で資産を引き継ぐことになり、大きな不平等が発生します。
不動産は資産額が大きいため、土地活用を行うことで節税はできるけれども、売却や分筆が難しくなることで、遺産を平等に分けにくくなってしまうのです。
相続は、遺産の分割で争われてしまうことが多いですが、その原因の多くは財産の中に分けにくい不動産が存在することが原因となっています。
相続後の分割方法

相続では、財産を相続人に分けることを分割と呼び、分割をしないままでいると、すべての財産は法定相続割合の共有で引き継ぐことになります。
法定相続割合とは、民法で定められた遺産分割割合のことであり、例えば相続人が2人の子だけであれば50%ずつが法定相続割合です。
共有のままにすると、特に不動産に関しては後々大きな問題に発展する可能性があります。
共有物件を売却するには共有者全員の同意が必要です。
共有名義の状態を放置した結果、二次相続、三次相続が発生し、子、孫、ひ孫と雪だるま式に共有者が増えていくと多人数共有物件となってしまい、連絡が付かない共有者も出てくるケースがあります。
共有者に連絡が付かない場合には、共有者全員の同意が得られないこととなり、売却ができない資産になってしまう可能性もあるのです。
そのため、不動産は相続人のうち誰か1人の単独所有物件にすることが望ましいと言えます。
法定相続割合以外の割合で財産を分割する方法としては、以下に示す「遺言」または「遺産分割協議」があります。
①遺言による分割
遺言とは、遺言者の生前の最終意思を尊重し、その意思の実現を死後に図る制度です。
被相続人(死亡した人)が遺産の分割割合を決めることができます。
遺言が残っていれば、相続人は原則として遺言に従って遺産を分割することになります。
もし、相続人が遺言の内容に不服があり、遺言で指定された方法以外で分割したいと考えた場合は、相続人全員の同意を前提に、遺産分割協議にて別の分け方とすることも可能です。
②遺産分割協議による分割
遺産分割協議とは、相続人の間で遺産の分け方を決める話し合いのことです。
遺言がない場合、または遺言があっても遺言とは異なる内容で分割したい場合には、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、話し合った内容を最終的に遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議により遺産の分割割合を決定するには、相続人全員の同意が必要です。
家族・親族間トラブルを考慮した対策

家族・親族間トラブルを考慮した対策としては、以下に示す「遺言書を残す」、「分割しやすい形を意識する」があります。
➊遺言書を残す
分割のトラブル対策としては、遺言書を残すことが効果的です。
遺言書は、仮に遺言書の内容に不満があっても相続人同士が遺産分割協議をすれば遺言書とは異なる内容で分割することができます。
遺産分割協議は相続人全員の同意がないと成立しないため、遺産分割協議が成立するということは揉めていないということです。
しかし、もし揉めてしまった場合は遺言書に従わざるを得なくなるため、遺言書を残しておくことは強力なトラブル防止策となるのです。
➋分割しやすい形を意識する
分割しやすい形を意識した土地活用を行うというのも対策のひとつです。例えば、子が2人いる場合には、土地に1棟の大規模アパートを建てるよりも2棟の小規模アパートを建てた方が遺産は分けやすくなります。
分けやすい形で土地活用を行えば、節税対策と併せて、遺産分割のトラブル対策も同時に行うことができます。
土地活用による相続対策をお考えの際は、
東建コーポレーションにご相談ください
以上、土地活用で生じる家族・親族間トラブルについて解説してきました。大きな投資を伴う土地活用は、遺産の中で不動産の割合を増やす結果に繋がりやすいです。
遺産の中に分けにくい不動産が存在することで、分割に関して家族や親族間でトラブルが発生することもあります。























 PAGE TOP
PAGE TOP



 電話でお問い合わせ
電話でお問い合わせ