
賃貸マンション経営では、中高層の建築物を建てることになるため、近隣トラブルの発生を防止するための対策を採る必要があります。
中高層の建築物は、周辺の日照条件を悪化させ、隣接する賃貸マンションと互いの室内が見えてしまう「見合い」の発生によってプライバシーを侵害する可能性も出てきます。
近隣住民から強い反対にあえば、計画を中断せざるを得ないことも考えられます。
一定規模以上の建築物を建てる場合には、近隣への配慮は重要事項です。
この記事では「賃貸マンション経営の近隣トラブルと対策」について解説します。
目次
近隣住民から寄せられる賃貸マンション建築計画への不安
中高層の建築物を建てる場合、近隣住民の間で以下のような反発や心配、不安が生じることがあります。
- ・高い建物が建つことで日照やプライバシーが侵害されるという反発
- ・工事期間中の騒音、工事車両の安全対策、振動に対する心配
- ・その建物がどのように使われ、どういう人が住むかという不安
日照に関しては、特に建物の北側に住む住民から強い反発を受けます。
プライバシーの侵害は、「見合い」が生じる可能性があるバルコニーが向いている側の住民から受けることが多いです。
景観が損なわれる場合は、景観が見えなくなる側の住民から反発を受けることがよくあります。
工事期間中の騒音や振動等も近隣住民の不安のひとつです。
騒音や振動は、新築工事よりも解体工事の方が多く発生するため、古い建物を解体してから新築を行う場合は特に近隣への十分な配慮が必要です。
建物の用途によっても、近隣住民に不安を与えることがあります。
例えば、ワンルーム賃貸マンションは若い人が住むことから「ゴミ出しマナーが悪くなる」、「地域のコミュニティに非協力的な人間が増える」という理由で反対する人も出てきます。
外国人向け賃貸マンションやペット可賃貸マンション、高齢者施設等でも反対する人はいます。
中高層建物の建築にあたっては、近隣住民からの反発をある程度想定した上で、計画を慎重に進めていくことが必要です。
近隣住民への基本対策
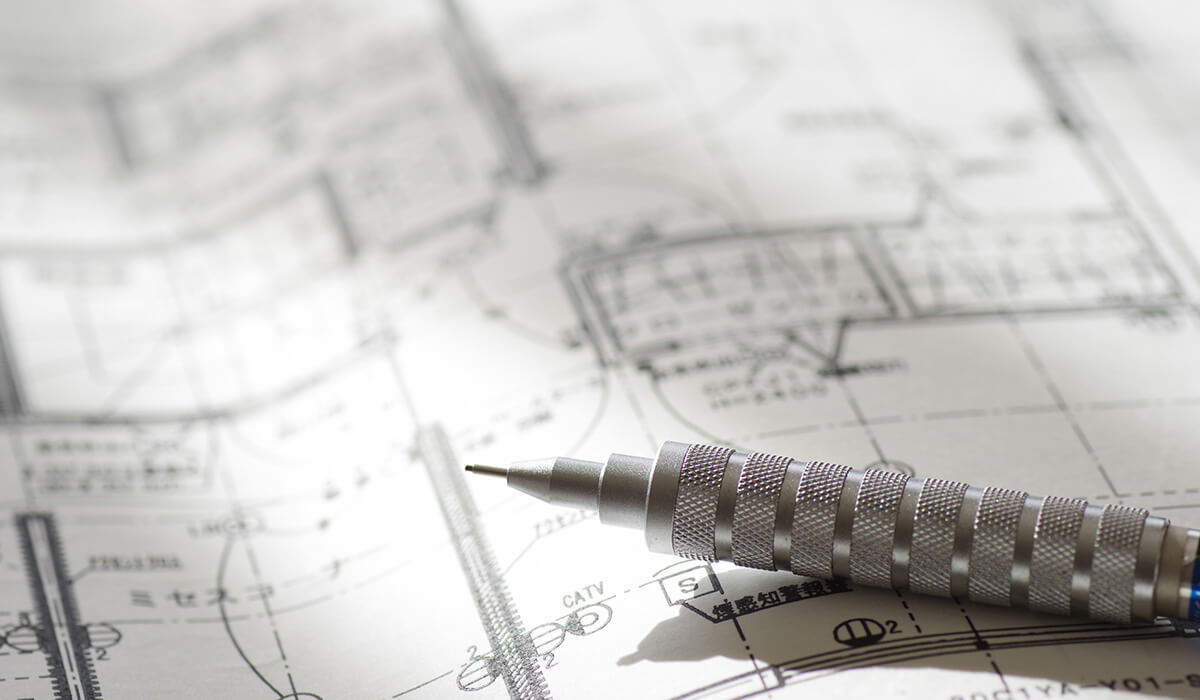
近隣住民への基本対策について解説します。
設計の配慮
近隣住民に対する対策は設計の段階から行っていくことが適切です。例えば、日照の問題で北側住民から反発を受ける可能性がある場合には極力建物を敷地の南側に寄せて建てるといった対策が考えられます。
近隣の家の中が見えてしまう状況の発生が問題になる可能性がある場合には、植栽を植えたり、バルコニーの柵の部分を外から見えない仕様にしたりといったことも対策となります。
隣地に近接している部分の窓は、曇りガラスにするといったことも近隣対策のひとつです。
事前の家屋調査
工事中は、振動が発生することで周辺の建物に損傷を与える可能性があります。
しかしながら、竣工後に近隣住民から「お宅の工事でわが家が壊れた」と主張されてもその事実を双方で証明することができません。
そこで、のちのトラブルを防ぐために行うのが着工前の家屋調査です。
着工前に近隣の一定の範囲で家屋調査を行い、建物の状況を確認しておきます。
着工前に家屋調査をしておけば、破損部分が工事によるものかどうかを推測することができます。
日ごろからの良好な関係の構築
日ごろからの良好な関係を構築しておくことも重要な近隣対策です。
特に、同じ地域で数年前に解体工事をしたような場合は近隣住民の間で解体時の騒音や振動の悪いイメージが残っている場合があります。
解体時の近隣への配慮が足らず当時のしこりが残ったままだと、新築工事で猛反発を受けることが起こり得ます。
近隣住民との関係が悪化していると無用な反発を受ける恐れがあるため、普段から良好な関係を築いておくことも重要な対策です。
工事中の近隣対策
工事中の近隣対策も重要です。
工事中の対策に関しては、まず近隣に工程表を配布し、いつから工事が始まり、いつ終わるかを案内する必要があります。
配布する工程表には、現場の工事監督の連絡先も記載しておくことが適切です。
何か問題が発生した場合、すぐに対応できる現場監督に直接連絡が行く体制とすることが望ましいと言えます。
着工前には近隣に挨拶を行い、大きな音や振動が発生する工程の時期を事前に説明しておくことも必要です。
また、近隣対策としてガードマンには人当たりが良く、柔軟に対応してくれる人を配置することも効果的な対策となります。
工事中のガードマンは、近隣住民に対して現場の顔とも言える存在です。ガードマンが愛想の良い人だと近隣からのクレームも少なくなっていきます。
施工会社に対して「ガードマンは人当たりが良く柔軟な対応ができる人を配置してください」と一言伝えておくことも対策のひとつです。
近隣説明の進め方

この章では、近隣説明の進め方について解説します。
①条例の確認
近隣への対応方法は、自治体の条例で定められています。
各自治体は「中高層建築物等の建築にかかる紛争予防条例」等の名称で独自のルールを定めていることが一般的です。
条例の内容は自治体によって異なり、一定規模以上の建物に対して「説明会を義務としている」場合もあれば「一定範囲に計画内容をポスティングするだけで良い」場合もあります。
まずは条例の内容を確認し、どこまで対応しなければならないかを知ることが必要です。
②説明資料の準備
条例で近隣説明やポスティング等が義務化されている場合には、必要な提示資料の内容も条例で定められていることが一般的です。
例えば、近隣への日照の影響を図示する日影図等が必須となっていることがよくあります。
必要な資料は設計者が作成します。
③想定Q&Aの作成とリハーサル
近隣説明会が必要な場合には、想定されるQ&Aも作成しておきます。例えば「階数を低くして欲しい」といった要望があった場合、どう答えるかを想定しておき、本番前には十分なリハーサルも必要です。
④町会長等への事前挨拶
近隣説明会の前には、事前に町会長等への挨拶を済ませておきます。
町会長には理解のある人も多いため、賃貸オーナー様の味方になってくれることもよくあります。
町会費を払って欲しい、祭りを手伝って欲しい等の要望があるため、前向きに対応して味方にすることが望ましいです。
賃貸マンション経営は、適切な土地活用コンサルティングの東建コーポレーションにご相談ください
以上、賃貸マンション経営の近隣トラブルについて解説してきました。
中高層の建物を建設する場合、ある程度は近隣住民からの反発や不安が想定されます。
想定される反発や不安を踏まえ「設計の配慮」や「事前の家屋調査」等の近隣対策を実施しておくことが適切です。
条例で近隣説明会の開催が義務化されている場合には、近隣説明会の準備をし、実施する必要があります。
近隣トラブルは発生させないことが一番ですので、慎重に対策していただければと思います。
東建コーポレーションでは、これまでの全国における施工実績と共に近隣住民の方々の声に耳を傾けてきました。
その経験値をもとに、オーナー様に代わり営業開発部員と建築技術部員による着工前の近隣挨拶を行い、工事スケジュールをはじめとした近隣住民の皆様の不安に配慮した丁寧なご説明を行うことで、トラブルに対し十分な対応・対策を心掛けています。
賃貸マンション経営をお考えの際は、東建コーポレーションにご相談ください。






















 PAGE TOP
PAGE TOP



 電話でお問い合わせ
電話でお問い合わせ