
資金計画とは、土地活用に必要な予算の総額を割り出し、投じることのできる自己資金と合わせて資金調達に関する全体の計画を把握することです。土地活用ではどのくらいの資金が必要で、用意する自己資金としては、いくらくらいが目安となるのでしょうか。
この記事では「土地活用の資金計画」について、アパート経営をモデルケースとして詳しく解説します。
目次
必要な頭金と自己資金
建築費と諸経費を合計したアパートの建設工事に必要な金額を「総事業費」と言います。
アパート経営を行う際は、自己資金と借入金(アパートローン)を用いて、総事業費を調達することが必要です。
スクロールしてご覧下さい
| 総事業費 | = | 建築費 | + | 諸経費 |
| 自己資金 | + | 借入金(アパートローン) |
総事業費のうち、建築費に対して5%程度の諸経費が発生します。
そのため、総事業費としては「建築費×1.05」程度の金額が必要です。
一方で、アパートローンを借りる場合は、金融機関から建築費の10%程度を頭金として求められることがよくあります。
頭金は自己資金の一部です。また、諸経費については、アパートローンに含めることができますが、一部、自己資金の中から用意する必要がある費用もあります。
よって、自己資金としては頭金(建築費の10%)と諸経費(建築費の5%)が必要となることから、建築費の10~15%程度を用意することが目安となります。
アパートの建築に必要な総事業費

アパート建築で生じる総事業費の内容について解説します。
建築費
総事業費の中で最も大きな金額を占めるものは建築費です。
建築費は建物の用途や面積、構造、材料、仕様等によって異なります。総事業費を抑えるには、過剰な設備や仕様の導入は避け、建築費を適正額とすることが最も効果的です。
設計料
建物を建てるには、設計料が発生します。
本来、設計会社と施工会社は異なりますが、土地活用専門会社は設計会社も兼ねていることが多いです。
土地活用専門会社が設計と施工も行う設計施工方式の場合であっても、設計料は必要となります。
設計料は土地活用専門会社に設計施工で依頼した場合、建築費の1~3%程度ですが外部の設計会社に依頼すると設計料はもっと高くなり、建築費の5~8%程度になることもあります。
現況測量費

建物を設計するにあたっては、その敷地の現況を測量する必要があります。設計のために行う敷地の実測や方角(真北)の調査、敷地内高低差等の測量のことを現況測量と呼び、費用の相場は、20~30万円程度です。
地盤調査費用
アパートを建てる場合、地盤調査(ボーリング調査)が必要となることが一般的です。
地盤調査は、地盤改良の必要性や杭工事の距離を決めるために行う測量であり、支持地盤までの深さを測ることが目的となります。
ただし、地盤調査の結果、杭工事や地盤改良が不要と判断されることもあります。ボーリング調査の費用は、1ポイントあたり40~60万円程度となり、測量するポイントの数や場所は、建物を設計してから決定されます。
水道分担金
水道分担金とは、水道を引き込む際に自治体に支払う費用のことで、新たに水道を使用する建物を建てる際に発生します。
水道分担金は、戸数が増えるほど高くなるのが特徴です。
金額は自治体や引き込み管の口径等によっても異なりますが、戸数の多い賃貸マンションの場合は400~800万円程度の金額になることもあります。
火災保険料
火災保険料とは、建物に付保する損害保険料のことを指します。
本来、保険料は毎年生じる費用ですが、複数年一括契約をした方が安くなることから、新築当初に複数年分をまとめて支払うことが多いです。また、アパート経営を行う場合、地震保険にも加入しておくのが基本です。
印紙税
工事の請負契約書やアパートローンの契約書を締結する際、印紙税が生じます。
印紙税は契約書に記載する金額によって税額が決まっており、その税額は下表の通りです。
スクロールしてご覧下さい
| 契約書に記載する金額 | 本 則 | 軽減税率(※) | |
|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 200円 | 非課税 | |
| 1万円以上 | 10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超 | 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超 | 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超 | 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 | 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 | 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超 | 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超 | 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超 | 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超 | 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 | |
| 金額の記載のないもの | 200円 | 200円 | |
※2027年3月31日まで
請負契約書は、2027年3月31日までに締結した契約書であれば軽減税率の印紙税が適用されます。
ローンの金銭消費貸借契約書には軽減税率は適用されず、税額は本則通りです。
登記費用
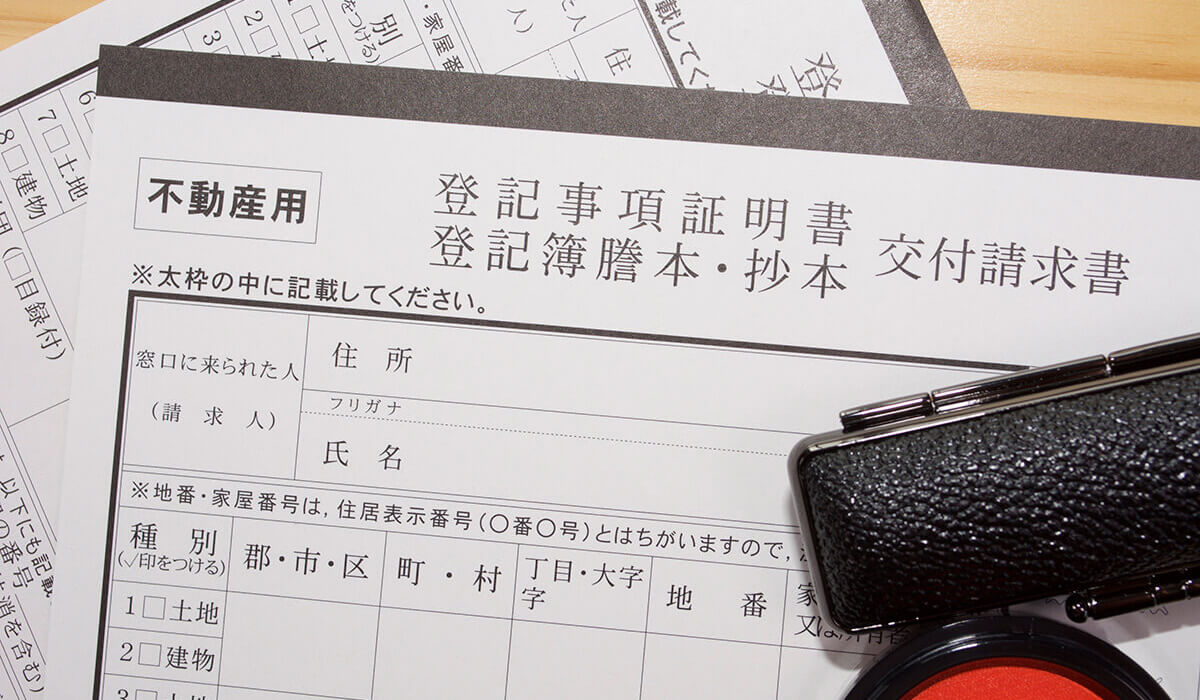
建物が竣工したら、登記を行います。
新築建物に所有権を設定するために行う登記のことを保存登記と呼びます。
建物の保存登記の登録免許税を計算する式は以下の通りです。
- 建物保存登記の登録免許税
- =
- 建物の固定資産税評価額
- ×
- 0.4%
建物の固定資産税評価額は、新築の請負工事金額の概ね50~60%程度となります。
また、アパートローンを利用する場合には、抵当権の設定登記も必要です。
抵当権とは、債権者(銀行)がその担保物件から優先的に弁済を受けられる権利のことを指します。
抵当権設定登記の登録免許税の求め方は以下の通りです。
債権金額とは、融資額のことを指します。
- 抵当権設定登記の登録免許税
- =
- 債権金額
- ×
- 0.4%
登記手続きは、司法書士に依頼することが一般的です。
司法書士に支払う手数料は、保存登記と抵当権設定登記を合わせて6~7万円程度が相場となります。
不動産取得税
不動産取得税の税額は、取得した不動産の価格(課税標準額)に税率を乗じて求めます。
- 不動産取得税
- =
- 取得した不動産の価格
(課税標準額※) - ×
- 税率
※通常、課税標準額は取得年分の固定資産税評価額を適用します。
(注)2027年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格の2分の1を課税標準額とします。
不動産取得税の本則税率は4%です。
ただし、2027年3月31日までは以下のように軽減されています。
スクロールしてご覧下さい
| 住宅関係 | 土地 | 3% |
|---|---|---|
| 建物 | 3% | |
| 住宅以外 | 土地 | 3% |
| 建物 | 4% |
土地活用の予算を把握する方法

土地活用の総事業費は、建築費を把握しないとなかなか見えてきません。建築費を把握するには、建物の設計をする必要があります。
土地活用では、土地活用専門会社が無料で設計プランを提案してくれることが一般的で、設計プランだけでなく、建築費と諸費用の初期費用や竣工後の収支計画も提案してくれます。
様々な数値を把握することができますので、土地活用に興味のある方はぜひ土地活用専門会社に相談してみてください。
土地活用は、適切な土地活用コンサルティングで
お応えする東建コーポレーションにご相談ください
以上、土地活用の資金計画について解説してきました。
土地活用では、自己資金として建築費の10~15%程度を用意することが目安です。
資金計画を立てるには、建物を設計することが必要となります。
総事業費を知りたい方は、土地活用専門会社に打診することをおすすめします。
東建コーポレーションでは、お客様にご満足していただける高品質な商品を提供できるように、全国に東名建築設計室を配備し、自社設計による設計体制を確立しています。
そのノウハウの蓄積により、正確な資金計画書のご提示、及びお客様のご要望に適切な土地活用コンサルティングをご提供します。
土地活用をお考えの際は、東建コーポレーションにご相談ください。






















 PAGE TOP
PAGE TOP



 電話でお問い合わせ
電話でお問い合わせ